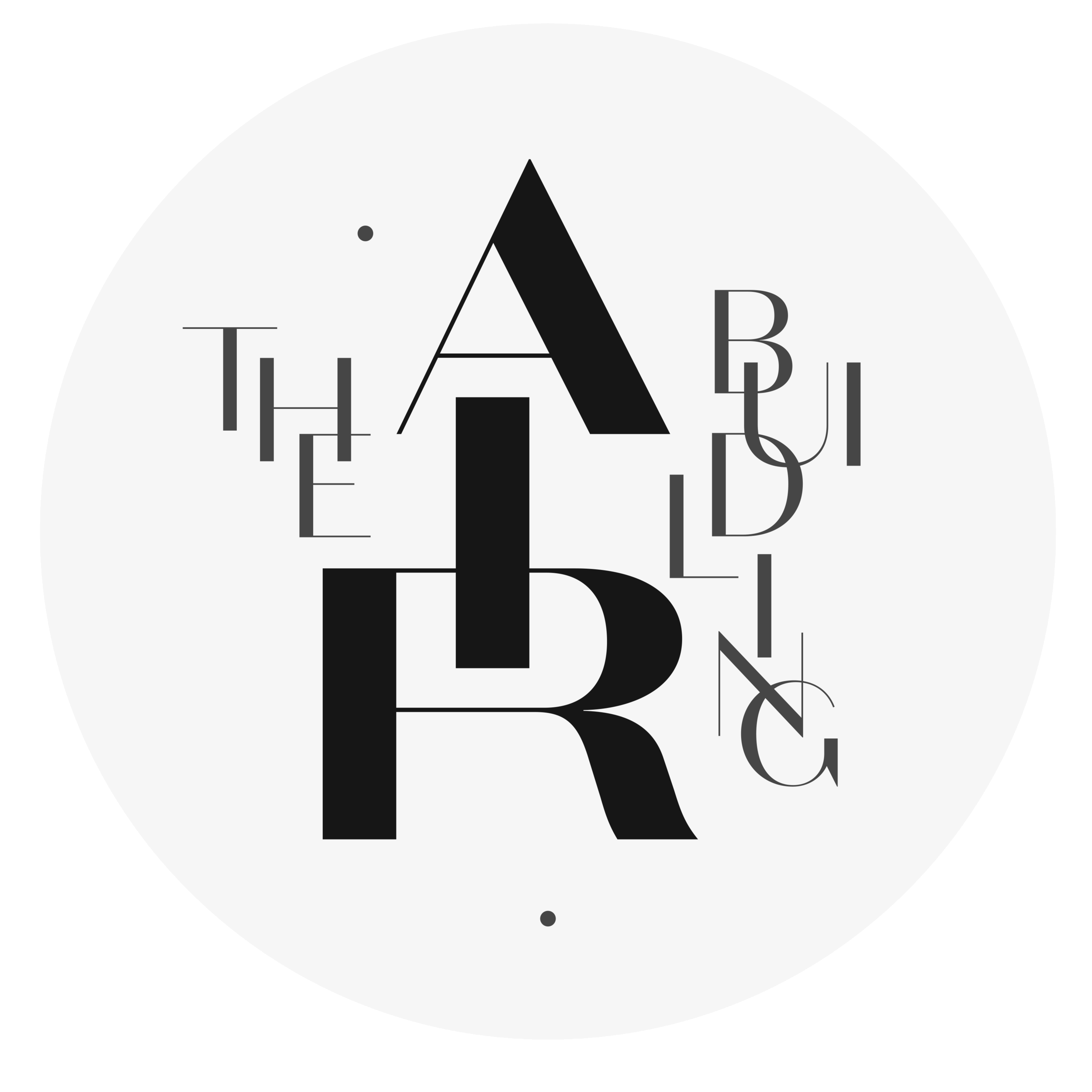THE STORY OF GILLES
『もしかすると彼女はロバートジョンソンが魂を差し出した悪魔なのかもしれない。』
そんな荒唐無稽なジョークを口にするほど彼は深く恋に落ちていた。
『まるで巨大な竜巻に飲まれた象でも見ているような気分だよ』と生まれて初めて経験する感情をなんとか言語にしてみようとするのたが、ステージ上での流麗かつウィットに富んだ演奏とは違い、そこに感心するような表現は何1つなかった。
そもそも言葉にすることになんの意味もない。人が人を愛した、というだけのことだ。しかし考えてみれば、その単純な現象をぼくたちは幾千の言葉にしたり、
音色に変えて伝達したり、そこに経済までもが生まれているのだからおかしなものだ。
彼にとってアジア系の女は初めてというわけではなかった。彼の奏でるトランペットが生み出す独特のスリリングな音色は、人種を問わず女性をうっとりさせる。
JAZZ仲間たちから”哀しみの恋人たち”と揶揄された取り巻きたちがいつも彼の楽屋にいたほどだった。
しかしレイコに出会って以来、彼はすっかりそんな情事には興味を失ってしまった。 ただ1人の女性を愛するという”至上の愛”が、すっかり彼の生きる目的になり、
それは音楽家としての在り方をも変えてしまった。
正確無比な音色を複雑なドラムパターンの隙間に落とし込んでいくことに全神経を注いでいた自身の演奏スタイルも、もう以前のように興味を持てなくなってしまった。
今はただ自分の奥深くから目を覚ました得体の知れない感情を空気の振動に変えて世界へ伝達し、それを自分自身も追体験的に理解しようとすることにしか
興味を持てなくなってしまったのだった。
レイコがニューヨークに滞在していた期間は半年ほどで、彼がSOHOのアパートで彼女と暮らしたのは最後の2ヶ月程度でしかなかったが、彼女がニューヨークを去った後、
彼女のことを想わない日は1日としてなかった。しかしちょうどその前の年あたりから数々の有名バンドからも声がかかり始め、ニューヨークでジャズマンとしての成功を掴もうと
していた彼にとって、日々のショウに集中することこそが何より大切なことだった。
僕も時折彼の演奏を見るためにSmokesに足を運んでいたので、彼の人気が日に日に大きくなっているのを感じていた。
しかし一方で、レイコにとっては異国の地で一人彼の帰りを待つのがルーティンになってしまい、日本での華やかな生活が恋しくなるのに長くはかからなかった。
ジャイルスが独立記念日を祝う盛大なパーティーでの演奏を終えてアパートに帰った時には、もう彼女の居た痕跡は何もかもなくなっていた。
しばらくの間は何もなかったかのように、彼はタバコに火をつけ、いつものようにレコードをかけようとしたが、今の状況に適切なナンバーは何一つ思いつかなかった。
彼が唯一の日本人の友達である僕に、東京行きの決意を告白してきたのはクリスマスムードが街を覆っていたとても寒い日だった。
空港へ向かう朝、ジャイルズは僕のアパートにしばしの別れを言うため立ち寄った。思い出話のほとんどはジャズのレコードの話か、お気に入りのバーの話だったが、
空港へ向かう時間が近くなるにつれて、彼はレイコについて話し始めた。東京にいる彼女と連絡を取り合っていること、レイコの父親が所有する元々製薬会社だった空きビルに2人で住む予定でいること。彼が何か核心的な事を避けて話しているであろう事はすぐに感じ取れたが、僕はそれについて何も聞かなかった。
僕が何を言ったところで彼の決意は変わらなかっただろうし、彼の新しい旅立ちを手垢のついた”常識的な意見”で汚したりはしたくなかった。
ぼくは「最後に少しだけ君の演奏が聴きたいんだが、お願い出来るかな」と伝えると、彼は少し黙ったあと、何も言わずにケースから愛用しているトランペットを取り出した。
その時の音色を僕は未だに忘れる事が出来ない。それはまるでレイコへの賛美と、彼自身の中の混沌とした感情が、記憶となって僕の身体の中に直接書き込まれるような不思議な感覚だった。後にも先にも僕はあの時のような経験をしたことはない。 演奏が終わると彼は、簡単な別れの言葉だけを告げて、タクシーに乗り込んでいった。
しかし部屋にはまだ誰かが居るような気配が残っていた。
僕は「神のご加護を」と呟いたあと、何をしていいのか分からずラジオをつけた。
ディスクジョッキーはマイルスデイビスの出たばかりのアルバム、Bitches Brewを訳も分からず大絶賛していた。
第2章へ続く